祝日について
日付 : 2023/11/04
作成者 : 田中遥貴
はじめに
久しぶりにブログを書きます。今回は趣味の紹介よりも知識を増やすための内容にしたいと思っています。そして、何かないかと探していたときにあることに気付きました。 今回の締切日は11月3日(間に合わず4日に変更)です。この日は、文化の日です。私は、祝日は学校が休みというイメージしかありません。そこで、今回は祝日について調べたいと思います。
祝日とは
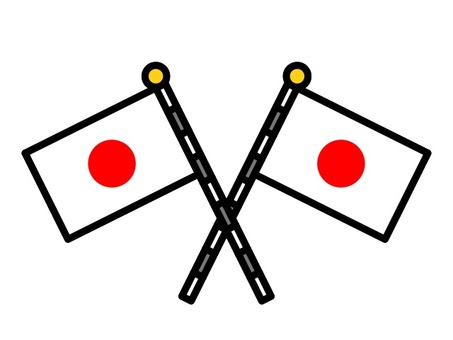
祝日[1]とは、「国民の祝日に関する法律(以下「祝日法」と記す)」という法律で定められています。 その第1条では、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と規定しています。 これは、祝日が休日の日だけでなく、国民が祝い、感謝し、又は記念する日であるということです。 現在、祝日は1年間で16日あります。1つずつ説明していきます。
-
元日
1月1日、年のはじめを祝う日です。
祝日法の制定当初から設けられています。 -
成人の日
1月の第2月曜日、おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます日です。
祝日法の制定当初から設けられています。青年男女に国家社会のため、さらには世界人類のために尽くそうとする自覚を持ってもらいたいとの願いが込められています。 -
建国記念の日
2月11日、建国をしのび、国を愛する心を養う日です。
昭和41年の祝日法改正により設けられました。建国をしのび、国を愛し、国の発展を期するという国民がひとしく抱いている感情を尊重して、国民の祝日とされました。 -
天皇誕生日
2月23日、天皇の誕生日を祝う日です。
祝日法の制定当初から設けられています。祝日法制定当初は、昭和天皇の誕生日である4月29日でしたが、平成元年2月に改正され、12月23日となりました。そして、現在は2月23日となりました。 -
春分の日
春分日、自然をたたえ、生物をいつくしむ日です。
祝日法の制定当初から設けられています。 -
昭和の日
4月29日、激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日です。
平成17年の祝日法改正により設けられました。 -
憲法記念日
5月3日、日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日です。
日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布され、昭和22年5月3日に施行されました。その施行日を記念としました。 -
みどりの日
5月4日、自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日です。
平成元年の祝日法改正により設けられました。始めは、天皇誕生日であった4月29日がみどりの日でした。平成17年の祝日法改正により、4月29日は昭和の日とされたため、5月4日に変更されました。 -
こどもの日
5月5日、こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日です。
祝日法の制定当初から設けられています。成人の日と同様に、特に次の時代の人々に大きな期待をかけているとされています。 -
海の日
7月の第3月曜日、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日です。
平成7年の祝日法改正により、平成8年から設けられました。 -
山の日
8月11日、山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日です。
平成26年の祝日法改正により、平成28年から設けられました。 -
敬老の日
9月の第3月曜日、多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日です。
昭和41年の祝日法改正により設けられました。 -
秋分の日
秋分日、祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日です。
祝日法の制定当初から設けられています。 -
スポーツの日
10月の第2月曜日、スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日です。
昭和41年の祝日法改正により設けられました。国民がスポーツに親しみ、その精神を通じて健康な心身を培って、明るく住みよい社会を建設することを願い、祝日とされました。 -
文化の日
11月3日、自由と平和を愛し、文化をすすめる日です。
祝日法の制定当初から設けられています。昭和21年に日本国憲法が公布された日であり、憲法において戦争放棄という重大な宣言をし、国際的にも文化的意義を持つ重要な日であることから、平和を図り、文化を進める意味で文化の日と名付けられました。 -
勤労感謝の日
11月23日、勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日です。
祝日法の制定当初から設けられています。
まとめ
今回は、私があまり知らなかった祝日の意味を調べました。これからは、それぞれの祝日の意味を理解して、生活していこうと思います。